高校英語リーディング④|論理構造をつかむ読み方で“話がつながる英語”に変える!
英語の長文を読んでいて「単語も文法もわかるのに、内容がつながらない…」と感じたことはありませんか?
実はその原因の多くは、文と文の“論理構造”を意識していないことにあります。英語の文章は「理由」「対比」「具体例」など、明確なつながりによって構成されています。
1. 「論理構造」とは何か?
「論理構造」とは、文章の中で文と文、段落と段落の関係を示す“つながり”のことです。
英語ではこの関係がとても明確で、次のようなパターンがよく見られます。
- 因果関係: because, so, therefore(理由→結果)
- 対比関係: but, however, on the other hand(意見の対立)
- 具体例関係: for example, such as, for instance(説明の補強)
この「つながり」を意識するだけで、英文の意味がスッと頭に入ってきます。
2. 因果・対比・具体例の読み方を身につけよう
英語の長文では、この3つのパターンを見抜くことがリーディング力向上の鍵です。
① 因果関係(because / so / therefore)
「なぜ?→だから」の関係を見抜けると、筆者の主張が明確に見えてきます。
例: He was tired because he studied all night.
→ 「徹夜で勉強したから、疲れている」という因果のつながり。
② 対比関係(but / however / on the other hand)
「AだけどB」という構造では、後半の意見が筆者の主張になることが多いです。
例: I like math, but my friend prefers history.
→ ここでは“好みの違い”という対立関係を表しています。
③ 具体例関係(for example / such as / for instance)
「たとえば〜」は、筆者の主張を補足する“説明のサイン”です。
例: Many animals, such as dogs and cats, are loved by people.
→ 「犬や猫のような動物」が「人に愛される」具体例として挙げられています。
3. 接続詞は“文と文をつなぐ道しるべ”
接続詞は、英文の論理関係を教えてくれるサインです。
- 接続詞を見つけたら、前後の文の関係を想像する
- 因果・対比・具体例のどれに当てはまるか考える
- 「前→後」のつながりを意識して読む
これを繰り返すことで、文章全体の“流れ”を自然に理解できるようになります。
4. 練習法:段落ごとに「関係」をメモする
長文を読むときに、段落ごとに以下のようにメモを取ると効果的です。
- 第1段落 → 問題提起(Why〜?)
- 第2段落 → 理由(Because〜)
- 第3段落 → 具体例(For example〜)
このように構造を意識することで、長文全体の流れが整理され、要約力もアップします。
5. 無料配布:論理構造練習ノート📙
このサイトでは、今回の内容を実践できる「論理構造リーディング練習ノート」を無料配布しています。
6. まとめ:英語は“つながり”で読むと見える世界が変わる!
単語や文法の知識だけでは、英語を「理解」することはできません。
英語を“話の流れ”として読むことで、文と文の関係が見え、内容理解もスムーズになります。
👉 次回は「速読と精読の使い分け方」で、さらに実践的な読解テクニックを紹介します!
この記事は、英語教育専門講師が解説しています。
正しいリーディング法で、英語が“読める”から“わかる”へ。


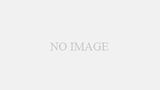
コメント