高校英語リーディング|速読と精読の使い分けで読解力アップ!
「英語の長文を読むのが遅い」「内容を理解できない」──そんな悩みを持つ高校生、多いですよね。
実は、英語リーディングでは「速読」と「精読」をうまく使い分けることで、理解力とスピードの両方を伸ばすことができるんです。
1. 速読と精読の違いを簡単に説明!
速読(Speed Reading)とは、文全体の意味をざっくりつかむ読み方。
キーワードを拾いながら「何について書かれているか」を素早く理解します。
→ 共通テストや模試など「時間との勝負」になる場面で効果的です。
精読(Careful Reading)とは、文構造・文法・語彙を正確に読み解く方法。
「なぜそう言えるのか?」「この単語の意味は何か?」を丁寧に確認します。
→ 難関大入試や、読解問題の根拠を探すときに欠かせません。
2. どちらが大事?それぞれのメリットと注意点
- 速読のメリット: 時間をかけずに全体像をつかめる。スコア型試験に強い。
- 速読の注意点: 内容の深い理解や文法チェックには向かない。
- 精読のメリット: 正確な理解・文構造・語彙力が伸びる。
- 精読の注意点: 時間がかかる。量をこなせないと読むスピードが落ちる。
3. 共通テスト・大学入試での使い分け例
たとえば共通テストの英語では、80分で約6,000語を読む必要があります。
このスピードに対応するには、すべてを精読するのは不可能。
そこで、最初に速読で全体像をつかみ、設問ごとに必要な箇所だけ精読するのが理想です。
一方、私立・国公立の二次試験では、設問が「なぜそう言えるのか」「筆者の意図は?」のように深くなるため、精読中心で根拠を探す力が求められます。
4. 速読&精読を両立するおすすめ練習法
速読と精読は、実はどちらかを選ぶものではなく、両方を鍛えると最強です。おすすめの練習法を紹介します👇
- ① 同じ英文を「速読 → 精読 → 速読」で読む
1回目は全体をざっと読む。2回目で文法・構文を確認。3回目でもう一度速く読む。
→ 理解の深さとスピードの両方が伸びます。 - ② タイマーを使って時間感覚を身につける
1文あたり何秒で読めるかを意識してみよう。共通テストでは、1問に使えるのは平均12〜15分程度です。 - ③ 精読ノートを作る
わからなかった文構造・単語をノートにまとめ、復習に活用。
「なぜこの文はそう訳すのか?」を説明できるようにすると最強です。
5. まとめ:場面によって読み方を切り替えよう!
英語リーディングでは「速く読む力」と「正確に読む力」の両方が必要です。
共通テストでは速読で全体像をつかみ、入試の記述問題では精読で根拠をとる。
この2つを使い分けられるようになると、英語力は一気に伸びます!
👉 関連記事:
📘 配布教材:「速読&精読トレーニングノート」も準備中!
easygoingedu.com で無料ダウンロードできます。


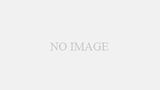
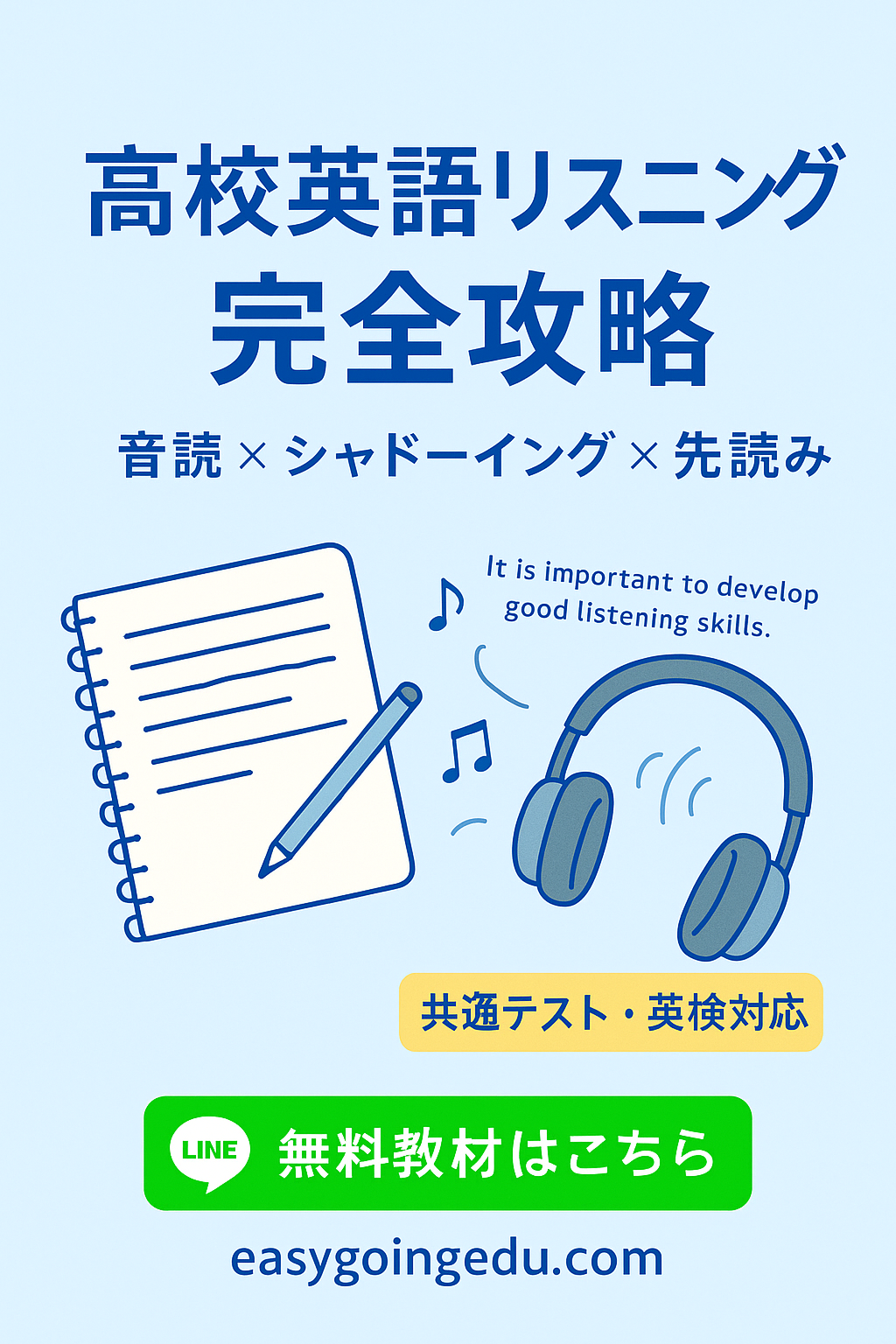
コメント